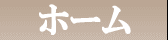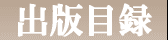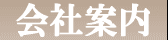出版目録
著者名検索
クリックで詳細が見られます。
麻海晶
アジア市民の会
麻生丈士
アリス・クック
石原静子
伊藤ルイ
「岩佐裁判の記録」編集委員会
内田 博
加藤 慶
きくちゆみ
グウィン・カーク
熊谷一乗
教育政策2020研究会
憲法ネット103
公教育計画学会
五本木シネ・クラブ
小西洋之
小宮山洋子
今野 東
塩崎文雄
澁谷利雄
島田 恵
シャロン・ラストマイアー
すがややすこ
鈴木勁介
戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会
瀧井宏臣
地域自立をすすめる会
寺田侑
土屋光男
都民党
中川登志男
中西広大
成澤宗男
日本教育政策学会
引地洲夫
樋口健二
平野伸人
広瀬 茂
ボルジギン・ブレンサイン
山崎隆敏
山本知佳子
ユ・ヒョヂョン
アジア市民の会
麻生丈士
アリス・クック
┗グリーナムの女たち──核のない世界をめざして(グウィン・カークと共編著)
池田 実石原静子
┗和光燦燦
磯貝ひろ子伊藤ルイ
「岩佐裁判の記録」編集委員会
内田 博
┗寺子屋通信(品切れ・再版未定)
海をつくる会
┗横浜・野島の海と生き物たち(品切れ・再版未定)
NPO法人会計基準協議会加藤 慶
┗情報メディア社会へのアクセス(松下慶太と共編著)
加藤 巌
┗アジアから学ぶ“よい”暮らし、“よい”人生(澁谷利雄と共編著)
神本みえ子きくちゆみ
グウィン・カーク
┗グリーナムの女たち──核のない世界をめざして(アリス・クックと共編著)
国祐道広熊谷一乗
┗転換期の教育政策(嶺井正也・国祐道広と共編著)
熊本一規教育政策2020研究会
憲法ネット103
公教育計画学会
公教育計画研究
┣第1号 公教育の現在と教育計画(2010)
┣第2号 地域主催と公教育(2011)
┣第3号 ソーシャル・インクルージョンと公教育計画(2012)
┣第4号 教育振興基本計画の現状と課題(2013)
┣第5号 公教育計画の現状と可能性(2014)
┣第6号 教育再生実行会議と公教育(2015)
┣第7号 戦後レジームから脱却(2016)
┣第8号 現代の貧困と公教育(2017)
┣第9号 進む教育の国家統制(2018)
┣第10号 教職員養成制度の旋回(2019)
┣第11号 公教育計画の現代的諸課題(2020)
┗第12号 コロナ禍の中の公教育計画を問う(2021)
┗第13号 公教育計画と教育労働の現在(2022)
┗第14号 特別支援教育中止勧告の衝撃と学校改革(2023)
国家秘密法を考える中野区民ず┣第1号 公教育の現在と教育計画(2010)
┣第2号 地域主催と公教育(2011)
┣第3号 ソーシャル・インクルージョンと公教育計画(2012)
┣第4号 教育振興基本計画の現状と課題(2013)
┣第5号 公教育計画の現状と可能性(2014)
┣第6号 教育再生実行会議と公教育(2015)
┣第7号 戦後レジームから脱却(2016)
┣第8号 現代の貧困と公教育(2017)
┣第9号 進む教育の国家統制(2018)
┣第10号 教職員養成制度の旋回(2019)
┣第11号 公教育計画の現代的諸課題(2020)
┗第12号 コロナ禍の中の公教育計画を問う(2021)
┗第13号 公教育計画と教育労働の現在(2022)
┗第14号 特別支援教育中止勧告の衝撃と学校改革(2023)
五本木シネ・クラブ
小西洋之
小宮山洋子
┣私の政治の歩き方(1)──タフでなければ変えられない
┣私の政治の歩き方(2)──すべての子どもたちのために
┣私の政治の歩き方(3)──「子ども手当」こうして作った
┗厚生労働大臣・副大臣742日
近藤昭一┣私の政治の歩き方(2)──すべての子どもたちのために
┣私の政治の歩き方(3)──「子ども手当」こうして作った
┗厚生労働大臣・副大臣742日
今野 東
塩崎文雄
澁谷利雄
┗アジアから学ぶ“よい”暮らし、“よい”人生(加藤巌と共編著)
島 泰三島田 恵
┗いのちと核燃と六ヶ所村(品切れ・再版未定)
市民連合/総がかり行動シャロン・ラストマイアー
┗インクルーシヴ教育に向かって 「サラマンサ宣言」から「障害者権利条約」へ(嶺井正也と共著)
障害児を普通学校へ・全国連絡会すがややすこ
鈴木勁介
戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会
瀧井宏臣
地域自立をすすめる会
┗ゴミ事典(品切れ・再版未定)
朝鮮大学校朝鮮問題研究センター在日朝鮮人関係資料室寺田侑
土屋光男
都民党
中川登志男
中西広大
┗学校選択制は学校の「切磋琢磨」をもたらしたか(濱元伸彦と共著)
中村文夫成澤宗男
日本教育政策学会
日本教育政策学会年報
┣第 7 号 ナショナリズムと教育政策(2000)
┣第 8 号 学力問題と教育政策(2001)
┣第 9 号 構造改革と教育政策(2002)
┣第10号 教育基本法と教育政策(2003)
┣第11号 日本の学校と教育政策(2004)
┣第12号 教育政策と政策評価を問う(2005)
┣第13号 教育改革と地方自治(2006)
┣第14号 教育の目標・成果管理(2007)
┣第15号 新学力テスト体制と教育政策(2008)
┣第16号 人口変動と教育政策(2009)
┣第17号 教育政策研究の視角と方法(2010)
┣第18号 教育と政治の関係再考(2011)
┣第19号 子ども・家族・教育政策(2012)
┣第20号 転機にある教育政策(2013)
┣第21号 教育ガバナンスの形態(2014)
┣第22号 新教育委員会制度と地方自治(2015)
┣第23号 多様な教育機会の確保(2016)
┗第24号 安倍政権下の教育政策(2017)
濱元伸彦┣第 7 号 ナショナリズムと教育政策(2000)
┣第 8 号 学力問題と教育政策(2001)
┣第 9 号 構造改革と教育政策(2002)
┣第10号 教育基本法と教育政策(2003)
┣第11号 日本の学校と教育政策(2004)
┣第12号 教育政策と政策評価を問う(2005)
┣第13号 教育改革と地方自治(2006)
┣第14号 教育の目標・成果管理(2007)
┣第15号 新学力テスト体制と教育政策(2008)
┣第16号 人口変動と教育政策(2009)
┣第17号 教育政策研究の視角と方法(2010)
┣第18号 教育と政治の関係再考(2011)
┣第19号 子ども・家族・教育政策(2012)
┣第20号 転機にある教育政策(2013)
┣第21号 教育ガバナンスの形態(2014)
┣第22号 新教育委員会制度と地方自治(2015)
┣第23号 多様な教育機会の確保(2016)
┗第24号 安倍政権下の教育政策(2017)
┗学校選択制は学校の「切磋琢磨」をもたらしたか(中西広大と共著)
坂東弘美引地洲夫
樋口健二
平野伸人
広瀬 茂
┗ SARS その時
広瀬 隆
┣ 危険な話──チェルノブイリと日本の運命
┣ 眠れない話──刻々と迫る日本の大事故
┣ 最後の話──死の灰と世紀末
┣ 国連の死の商人
┣ 地球温暖化説はSF小説だった
┗ 日本の植民地政策とわが家の歴史
フォーラム平和・人権・環境┣ 眠れない話──刻々と迫る日本の大事故
┣ 最後の話──死の灰と世紀末
┣ 国連の死の商人
┣ 地球温暖化説はSF小説だった
┗ 日本の植民地政策とわが家の歴史
ボルジギン・ブレンサイン
┗境界に生きるモンゴル世界(ユ・ヒョヂョンと共編著)
松下慶太
┗ 情報メディア社会へのアクセス(加藤 慶と共編著)
嶺井正也
┣現代教育政策論の焦点
┣転換点にきた学校選択制
┣選ばれる学校・選ばれない学校──公立小・中学校の学校選択は今(中川登志男と共編著)
┣学校選択と教育バウチャー 教育格差と公立小・中学校の行方(中川登志男と共著)
┣公教育における包摂と排除(国祐道広と共編著)
┣転換期の教育政策(熊谷一乗・国祐道広と共編著)
┣インクルーシヴ教育に向かって 「サラマンサ宣言」から「障害者権利条約」へ(シャロン・ラストマイアーと共著)
┣公教育改革への提言(中村文夫と共編著)
┗市場化する学校(中村文夫と共編著)
宮盛邦友┣転換点にきた学校選択制
┣選ばれる学校・選ばれない学校──公立小・中学校の学校選択は今(中川登志男と共編著)
┣学校選択と教育バウチャー 教育格差と公立小・中学校の行方(中川登志男と共著)
┣公教育における包摂と排除(国祐道広と共編著)
┣転換期の教育政策(熊谷一乗・国祐道広と共編著)
┣インクルーシヴ教育に向かって 「サラマンサ宣言」から「障害者権利条約」へ(シャロン・ラストマイアーと共著)
┣公教育改革への提言(中村文夫と共編著)
┗市場化する学校(中村文夫と共編著)
山崎隆敏
山本知佳子
ユ・ヒョヂョン
┗境界に生きるモンゴル世界(ボルジギン・ブレンサインと共編著)
リタ・マリー・ジョンソン